天の川の中にひっそりと輝く球状星団—その姿は、まさに「宇宙の宝石」
と呼ぶにふさわしい存在です。
中でもM13(ヘルクレス座)とM22(いて座)は、北天と南天を代表
する球状星団として、長年にわたって天文ファンの心をつかんできまし
た。
今回は、これらの球状星団の魅力を解説するとともに、最新スマート
望遠鏡「VesperaⅡ」を使って実際に撮影した体験を、ブログ形式
でお届けします。
タイトル画像 M13 球状星団 VesperaⅡ 2025年6月5日
撮影者 静岡県 Jhosua氏
ブログ村ランキング参加中、応援クリックお願いします
にほんブログ村

M13:北天最大の宝石


M13 球状星団 ヘルクレス座 VesperaⅡの撮影 2025年6月5日撮影 撮影者 静岡県 Jhosua 氏
M13(ヘルクレス座大球状星団)は、北半球でもっとも
有名な球状星団です。
その特徴を簡単に紹介しましょう。
- 特徴:およそ50万個の星が直径約100光年の範囲に密集
- しており、星がぎっしり詰まったその姿は、まるで宝石箱
- をのぞき込んだようです。
- 美しさでは「全天一」と評され、小口径望遠鏡でも周縁部
- の星々がざらざらと見えるのが大きな魅力です。
- 観測のポイント:日本では夏に南中し、天頂付近に達する
- ため大気の影響が少なく観測好機です。
- シーイングが良ければ中心部の星も分解され、球状に広がる
- 星の立体感に圧倒されることでしょう。
- 肉眼でもうっすら確認でき、ファインダーでの導入も比較的
- 容易です。
M22:いて座の輝き


M22 球状星団 いて座 VesperaⅡの撮影 2025年6月5日撮影 撮影者 静岡県 Jhosua 氏
M22(いて座大球状星団)は、南天を代表する名球状星団です。
全天で最初に発見された球状星団としても知られています。
特徴:星数は約7万個とM13よりやや少ないものの、楕円形の独特
な形状と明るさで強い存在感を放ちます。
条件が良ければ肉眼でも観測可能で、いて座の星々の中でも際立つ
光を放っています。
観測のポイント:λ星(ラムダ星)から北東約3度に位置し、20cmクラスの
望遠鏡を使えば中心部の星々まで分解され、「泡粒のように」浮かび上がる
姿に感動すること間違いなしです。
スマート望遠鏡「VesperaⅡ」での撮影体験
今回、M13とM22の撮影にはVaonis社の最新スマート望遠鏡
「VesperaⅡ」を使用しての撮影です。
■驚くべき自動化機能
■アプリ操作だけで撮影完了:スマホアプリから天体を選ぶだけで、
自動導入・追尾・スタッキング・ノイズ除去までを完全自動化。
■都市部でもOK:光害のある地域でも、驚くほど鮮明な画像を
得ることができました。
■高精細な天体写真が自宅で!
■8.3メガピクセルのSONY IMX585センサーを搭載し、ライブ
モザイクモードでは最大24メガピクセルの広域撮影が可能。
球状星団の「星の密度感」「構造美」をリアルにとらえる力は、
小型望遠鏡の概念を覆します。
実写レビュー
M13の撮影結果
中心部の高密度な星々が美しく分解され、微光星もくっきり。
まさに「宇宙の宝石」と呼ぶにふさわしい構図。
スタッキング処理により、背景のノイズが極めて少なく、
深宇宙の静寂さを感じられます。
M22の撮影結果
特有の楕円形状と立体感が明確に写り、眼視観測では気づき
にくいディテールまで再現。
中心部の星々の分離も良好で、「泡粒の集まり」のような
印象そのままに記録されました。
まとめ
自宅から楽しむ「宇宙の宝石」
M13とM22は、その壮大さと美しさ、そして長い観測史により、
多くの天文ファンを魅了してきました。
そして今、その美しさを手軽に記録し、共有できる時代が訪れて
います。
VesperaⅡの登場により、かつては専門家や大型機材が必要だった
高精細な天体撮影が、庭先からでも実現可能となりました。
これから天体観測を始めてみたいという方にも、すでに何年も星を
追いかけてきた方にも、「スマート望遠鏡」は新たな宇宙の扉を開
いてくれることでしょう。
📸 あなたも今夜、宇宙の宝石を撮ってみませんか?
VesperaⅡでの観測体験が、きっと星空へのまなざしを変えてく
れます。
撮影画像の提供を頂いた静岡県のJhosua氏には誌面にて感謝します。
VesperaⅡの購入はこちらからできます
Vesperaの購入はこちらから
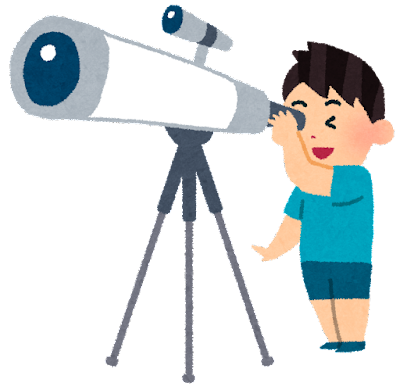
スポンサーサイト
ドメイン取得とホームページ作成には
ブログ作成には



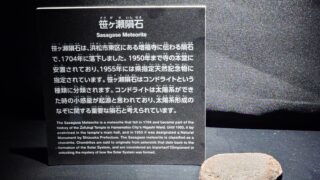


コメント